近年になり寒暖差がぎっくり腰のリスクを高めるとわかってきました。
とくに春と秋の季節の変わり目は、寒暖差ぎっくり腰を発症しやすいため注意が必要です。
本記事では気象庁のデータをもとに寒暖差ぎっくり腰のリスクを解説します。
寒暖差とは

寒暖差ぎっくり腰に関して、以下2つの気温差に着目する必要があります。
一般に気温差と聞くと、朝晩と日中の気温差をイメージしがちです。
しかし、寒暖差ぎっくり腰に関しては、日ごとの気温差に気をつける必要があります。
寒暖差ぎっくり腰で日ごとの気温差が重要な理由

寒暖差ぎっくり腰で日ごとの気温差が重要な主な理由は以下の2つです。
厚生労働省の調べでは、ぎっくり腰が8時~11時くらいに多く発生するとわかっています。
前日に比べ気温が大きく下がると、就寝中に体温が下がり筋緊張が生じます。
そのタイミングで布団から起き上がった際に、ぎっくり腰が多発する傾向にある訳です。
また、気温差で自律神経のバランスが乱れると、血行不良により身体の回復力が低下します。
寝起きにぎっくり腰が多いのは、筋緊張に回復力の低下が加わるためです。
日ごとの気温差ランキング
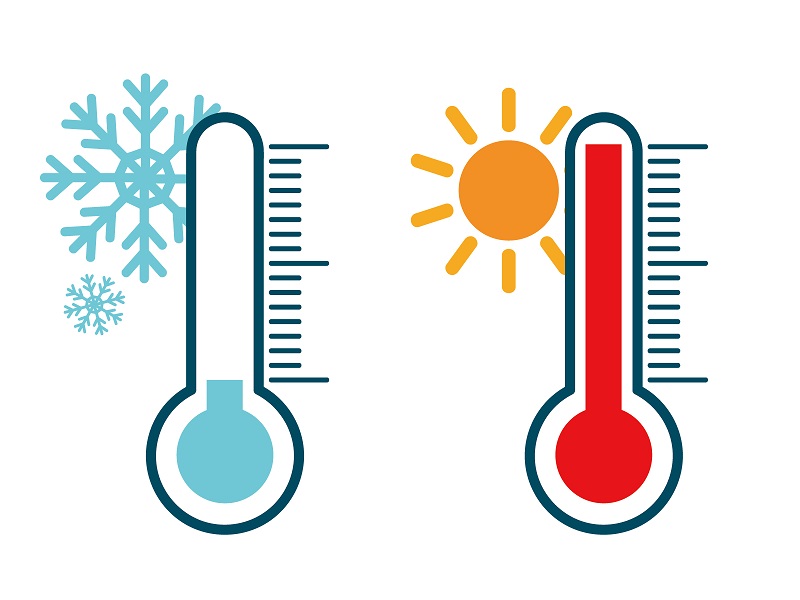
2024年の気象データによると、季節ごとの気温差(東京都の平均)は以下のとおりです。
| 1日の気温差 | 日ごとの気温差 | |
|---|---|---|
| 春 | 6.0℃ | 22.9℃ |
| 夏 | 8.3℃ | 17.2℃ |
| 秋 | 7.4℃ | 18.7℃ |
| 冬 | 8.5℃ | 18.5℃ |
春は気温差が大きい季節と言われますが、上記の表から大きいのは日ごとの気温差とわかります。
1日の気温差で見ると、春は四季のなかでもっとも小さいのが特徴です。
春にぎっくり腰が増えるのは、前日に比べて冷え込む日が多いためと考えられます。
秋は春に次いで日ごとの寒暖差が大きく、ぎっくり腰が増える季節の1つです。
夏にぎっくり腰が比較的少ない理由

夏にぎっくり腰が少ない理由は気温が高いためです。
7~9月の平均気温(東京都)は26.9℃、最高気温の平均は35.5℃です。
熱帯夜も平均で22日あり、全体的に気温が高い日が続く傾向にあります。
気温が高いと筋肉は緩みやすいため、ぎっくり腰のリスクが比較的低くなります。
冬にぎっくり腰が比較的少ない理由

冬場は四季のなかで1日の気温差がもっとも大きく、平均気温が低い季節です。
しかし、ぎっくり腰の発生件数は春・秋ほど多くありません。
理由としては厚着をしたり、室内の温度を高く設定したりすることが挙げられます。
また、温かい飲食物物で深部体温が上がることも、ぎっくり腰が比較的少ない理由の1つです。
寒暖差ぎっくり腰の予防法

寒暖差ぎっくり腰を予防するためには、以下の3点を意識する必要があります。
それぞれについて解説します。
自律神経のバランスを整える
寒暖差ぎっくり腰を予防するためには、自律神経のバランスを整える必要があります。
自律神経のバランスの乱れを防ぐためには、以下3つのポイントを押さえておきましょう。
ストレスをため込まない

ストレスは自律神経のバランスを乱す大きな原因です。
精神的ストレスはもちろん疲労や風邪、気温差など身体的ストレスにも注意しましょう。
ストレスの自覚がなくても、たまには趣味に没頭したり、リラックスしたりすることが大切です。
質の高い睡眠を意識する
自律神経のバランスを整えるためには、質の高い睡眠を意識しましょう。
睡眠の質を高める簡単な方法が、早寝早起きを意識して朝日を浴びることです。
朝日を浴びると体内時計がリセットされ、自律神経のバランスを整えやすくなります。
日中に適度に身体動かすことも、睡眠の質を高める際に有効です。
就寝前にスマホの明るい画面を見ない

自律神経の乱れを招かないためにも、就寝前にスマホの明るい画面を見るのは避けましょう。
暗い部屋でスマホの明るい画面を見ると、脳が興奮して睡眠の質が低下するためです。
就寝の1時間前にはデジタル機器を遠ざけ、リラックスした気分で布団に入るのがおすすめです。
就寝中に身体を冷やさない
寒暖差ぎっくり腰の発症を避けるためには、就寝中に身体を冷やさないようにしましょう。
就寝中に身体が冷えると、筋肉が硬直して朝方のぎっくり腰の発症リスクを高めます。
翌日の天気予報を見て、朝方冷えるようであれば暖房のオンタイマーを利用するとよいでしょう。
ストレッチで筋肉を柔軟に保つ

寒暖差ぎっくり腰を予防するためには、ストレッチで筋肉を柔軟に保つのがおすすめです。
柔軟な筋肉は負荷がかかっても断裂しにくい傾向にあります。
とくに股関節やおしり回り、太もものストレッチがぎっくり腰の予防に効果的です。
春と秋は寒暖差ぎっくり腰に注意が必要です

気象庁のデータを分析すると、春と秋は日ごとの寒暖差が大きいことがわかりました。
寒暖差で自律神経が乱されると、血行不良や筋緊張によってぎっくり腰のリスクが増加します。
翌朝の冷え込みが強ければ強いほど、寒暖差ぎっくり腰のリスクが高くなります。
春・秋の季節の変わり目は、翌日の天気予報を確認して寒暖差ぎっくり腰を予防してください。





